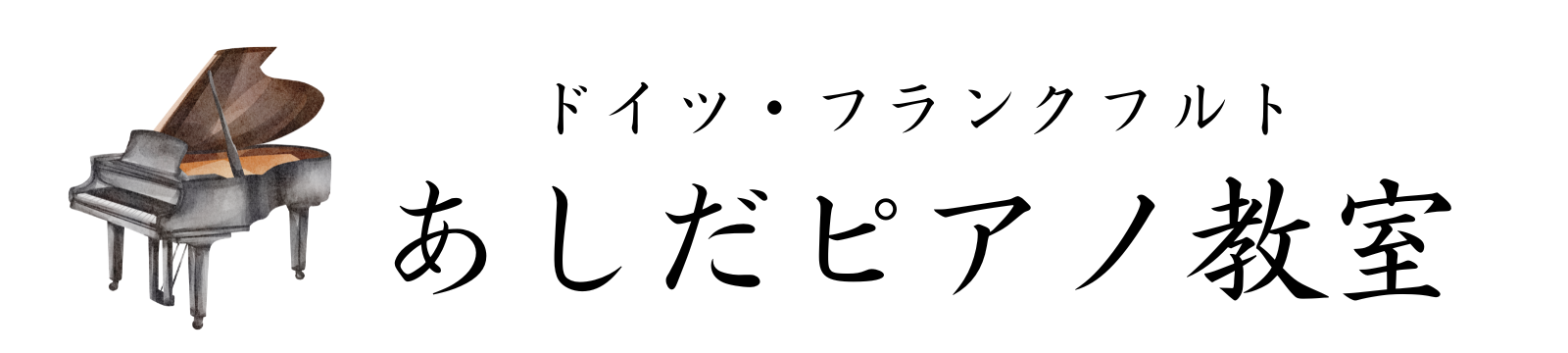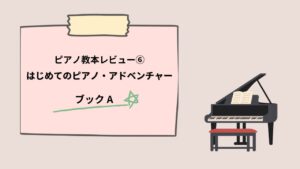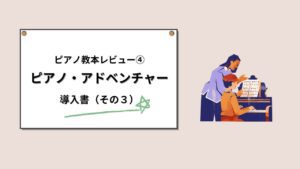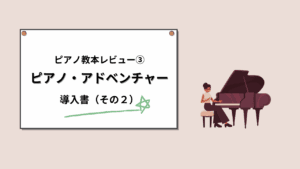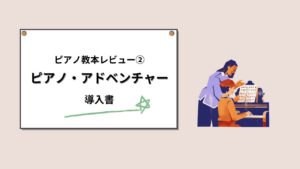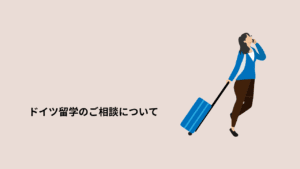※本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。
先日ピアノ・アドベンチャーの導入書について書きました。
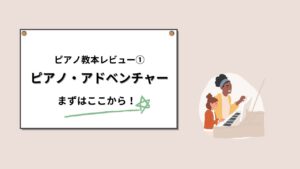
今日は、導入書の次に使うレベル1について書きたいと思います。
ピアノ・アドベンチャーのレベル分けについて
さて、レベル1についてお話しする前に、ピアノ・アドベンチャーの基本的な構造について説明します。
ピアノ・アドベンチャーのレベル分けは独特で、以下の順番になっています。
導入書(※)
↓
レベル1
↓
レベル2A
↓
レベル2B
↓
レベル3
↓
レベル4&5(4と5が一冊になっている)
※導入書の代わりに、「はじめてのピアノ・アドベンチャー」の A ~ C を使うこともできます。
ピアノ・アドベンチャーは All in two シリーズで、各レベルが「レッスン&セオリー」と「テクニック&パフォーマンス」の2冊に分かれています。
つまり、全課程をくまなくやるなら計12冊(!)必要になるということですね。
ちなみに、 Alle in two シリーズは日本国内のみのようで、英語版は第2版以降「レッスン」「セオリー」「テクニック&アーティストリー(表現力)」「パフォーマンス」の4冊に分かれています。
つまり、全過程をくまなくやるなら計24冊(!!)必要になるということですね。
英語版も第1版は All in two シリーズだったのですが、恐らくもう出版されていない(在庫限りの)ようです。
私は今のところレッスン&セオリーしか使用していませんので、今回もレッスン&セオリーに限って書きます。
ピアノ・アドベンチャー レッスン&セオリー レベル1
ピアノ・アドベンチャーの導入書は横長でしたが、レベル1は縦長の教本になります。
ピアノ・アドベンチャーのすべてのレベルで言えることですが、「レッスン&セオリー」と「テクニック&パフォーマンス」の見た目が容易には区別がつかないので、間違えて別の本を買わないように注意が必要です。
レベル1は10のユニットに分かれています(私の訳なので、実際の題名は異なることがあります)。
ユニット1:レガートとスタッカート
ユニット2:ト音記号のファ・ラ・ド・ミ
ユニット3:ト音記号のドレミファソ
ユニット4:音程(2度、3度、4度、5度)
ユニット5:二分休符と全休符
ユニット6:シャープとフラット
ユニット7:トニカとドミナント
ユニット8:Cコード( I の和音)
ユニット9:属七の和音
ユニット10:Gの五本指スケール
巻末付録:スケールと和音のウォーミングアップ(C、D、E、F、G、A)
ユニット2でいきなり「ファラドミ」が出てきているのが特徴的ですが、これは英語だと「F-A-C-E」となり、つまり “face(顔)”という言葉遊びで音名を覚えさせようとしています。
日本人の子どもにはこの語呂合わせもさすがにピンときませんが、ト音記号の第1~4間の音を最初にまとめて覚えてもらうというのは良いアイディアだと思います。
(参考)ピアノ・アドベンチャー 導入書 で音が出てくる順番
と、ここでこれも重要な情報かと思ったので、ピアノ・アドベンチャーで新しい音が出てくる順番を書いておきます(導入書の記事でも書けばよかったですね)。
まず導入書はユニット4から五線譜が始まります。一番最初に、右手は真ん中のドーソ(1と5の指)、左手は真ん中のドーファ(1と5の指)から始まります。これも独特ですね。
ユニット5では右手のドーソの間の音(レミファ)が一度に出てきます。
ユニット6で左手のシラソが追加されます(ただし1曲につき1音ずつ追加される感じです。いっぺんにではありません)。
ユニット8で左手のドレミが一気に追加されます。これで C ポジションが可能になります。ここまでは基本的にミドル C ポジションですが、指番号が特定の音と結びつかないように、随所に工夫がなされています。
ピアノ・アドベンチャー レベル1 で音が出てくる順番
レベル1では、こんな感じで音が増えていきます。
ユニット1の最後に右手にラが追加されます。イ短調の曲で、ラは4の指で弾くことになっています。
ユニット2で、前述の F-A-C-E (ファラドミ)が一気に追加されます。
ユニット3で、ファラドミの間のレが追加。次の曲でミのすぐ上のファとソが追加されます。
ユニット4~9まで新しい音の追加はなく、ユニット10で左手の低いソが追加となり、G ポジションに入ります。
ピアノ・アドベンチャー レベル1 音符の種類
ピアノ・アドベンチャーのレベル1では、四分音符より小さい音価は出てきません。
レベル2Aで初めて八分音符が出てきます。
ピアノ・アドベンチャー レベル1 進度について
簡単に比較はできませんが、だいたいバスティンのオールインワンの 1B がピアノ・アドベンチャーの 2A レベルに相当するのではと思います。
実際に、この2つの教本で出てくる曲がかぶっているところがあります(ト長調のメヌエットとか。余談ですが、こういった有名なメロディーを両手で分割して弾かせる曲がたまにありますが、両手で弾くと逆に難しくないですか?)。
私の印象を言わせてもらうと、レベル1はとにかく丁寧すぎるくらい丁寧です。
生徒さんにとって、だけでなく、先生にとっても親切設計なのがピアノ・アドベンチャーの特徴です。
指導のポイントや、同じ曲の違った活用法がしっかり書かれているので、この曲で何をレッスンしたらよいのかわからない、ということはまず起こりません。
また、これまでの私の経験上、生徒さんがついてこれなくてドロップアウトした、ということもありません。家でまったく練習してこない生徒さんはさすがに難しいと思いますが、週に数回でも練習する生徒さんなら、ピアノ・アドベンチャーが難しくてドロップアウトすることはまずないと思います。
ただ、逆にそれなりに練習をしてきてくれる生徒さんだと、もう少しサクサク進めてもよいのかなと思います。
生徒さんに合わせてピアノ・アドベンチャーを活用するには
生徒さんの状況に合わせてピアノ・アドベンチャーを使うには、何よりもユニットの構成を最初に理解しておくことです。
各ユニットのテーマ事項が理解できたら、すべての曲を弾いていなくても次へ進む、逆にまだ定着していないようだったらもう1曲弾く、くらいのテンポで進めていくとちょうどいい進度になるかと思います。
これはあくまでも私のやり方ですが、その曲でなくても説明ができるもの(拍子記号や休符の種類など)はスキップしたりしています。
速ければいいというものではもちろんないのですが、私は個人的に、できるだけ教本を使っている期間を短くしたいと考えているので、全員が全員、教本の曲を全曲弾かなければならないとは思っていません。
数こなし、という考え方もありますが、同じ数こなしなら教本の曲でなく、クラシックのオリジナル作品をたくさん弾いてほしいと思っています。
というわけで、ピアノ・アドベンチャーは進め方次第でいろんなタイプの生徒さんに合わせることができるのがよいと思っています。
ご興味のある方はぜひ一度手に取ってみてください。
↑↑↑こちらはテクニック&パフォーマンスです。買い間違いに注意。