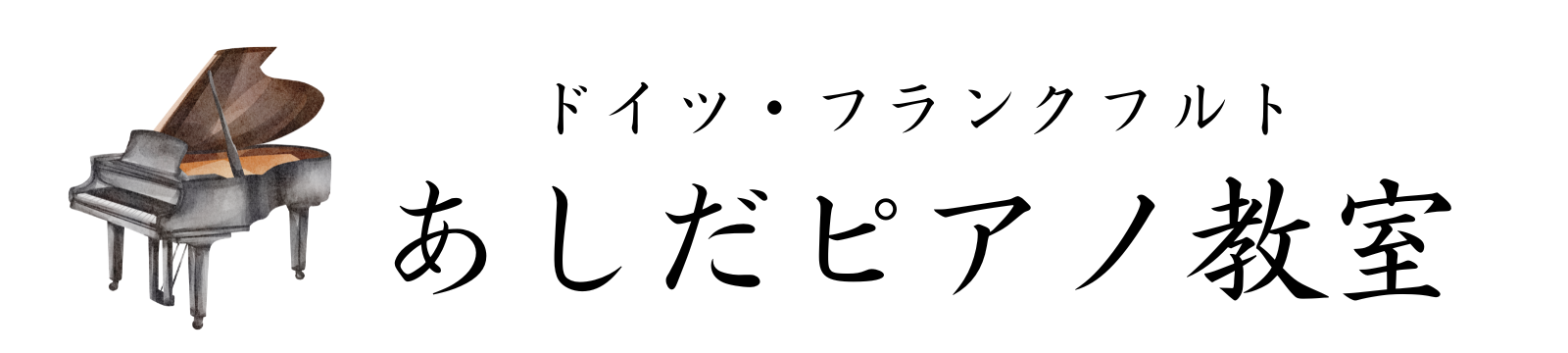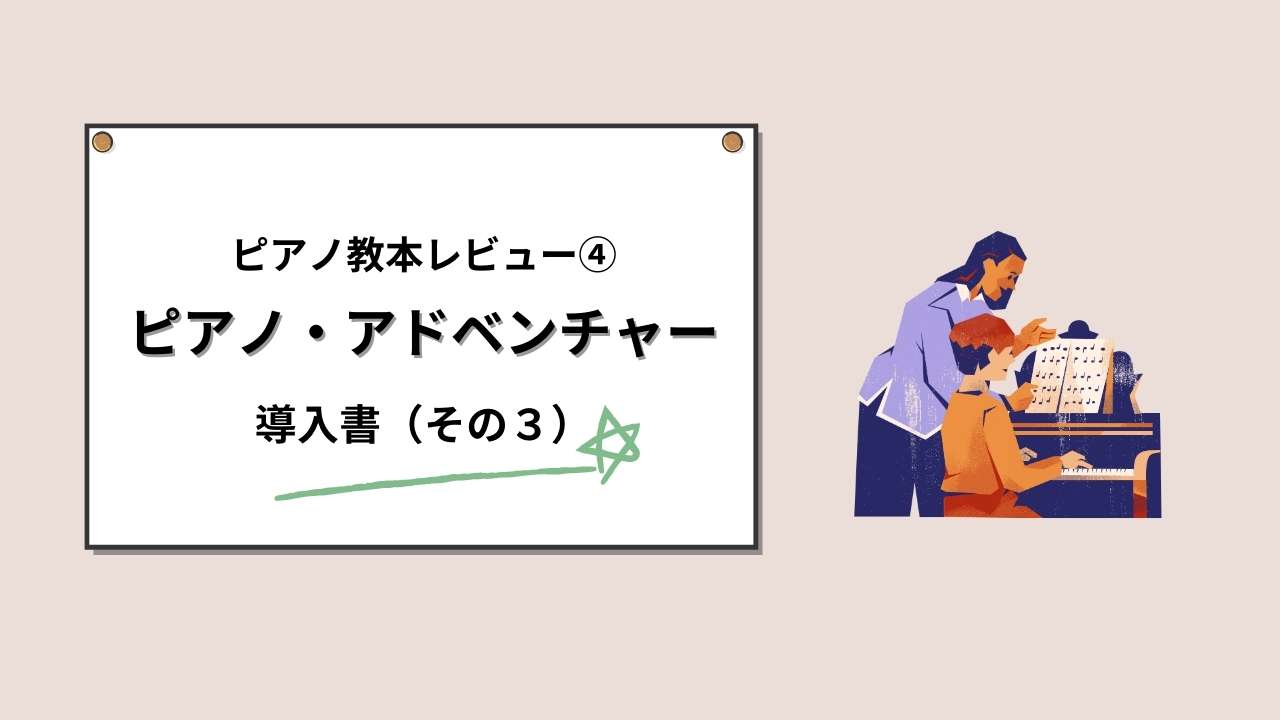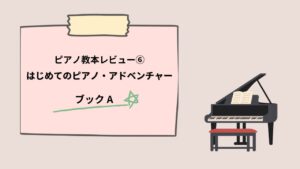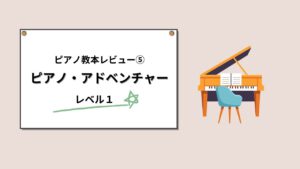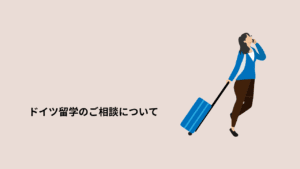これまでピアノ・アドベンチャーの導入書について色々書いてきました。
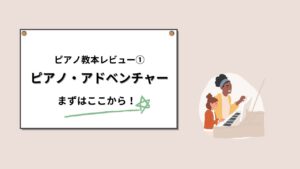
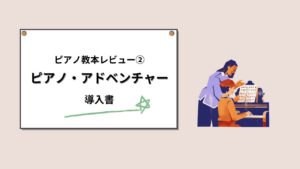
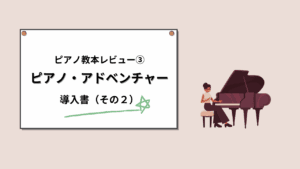
今回はようやく最終回で、ピアノ・アドベンチャーの魅力の1つであるアンサンブルについて書きたいと思います。
ピアノ・アドベンチャーはアンサンブルが楽しい
前回の記事でも書きましたが、ピアノ・アドベンチャーは伴奏がとてもおしゃれです。
日本の教本でも、初歩の段階で伴奏が書かれたものはありますが、どちらかというと V7→I の動きがメインかと思います。
ピアノ・アドベンチャーの場合、伴奏する側もハッとするような和声進行やリズムなどが出てきて、生徒さんがまだ数音しか習っていない段階でも、伴奏をつけたとたん音楽の世界がぐっと広がります。
導入の段階では「学習」よりも「体験」に重きを置きたいので、この単純な音の並びにこんなすてきなハーモニーが隠れていたんだなぁと感じてもらえると、1回1回のレッスンがとても有意義になります。
ただし、その分伴奏は(日本の教本に比べれば)やや難易度が高めです。初見が苦手な人は練習が必要かもしれません。
でも逆に、この導入書を通じて伴奏をしていると、即興で伴奏をする時の引き出しも広がっていきます。
音源アプリも便利
ピアノ・アドベンチャーにはCDやアプリの音源もあります。自宅でも使ってもらうと楽しいと思います。
私の教室では英語の方が慣れている生徒さんがいるので、アプリ内で色々な言語が選べるのも便利です。
たいてい、ピアノ・アドベンチャーを導入した当初はみなさん、「この音源いいですね!」と感動してくれるのですが、セットアップが面倒なのか、こちらから声かけしない限りだんだん音源のことは忘れられるようです。
音源だと、ミスをしてもずれてもどんどん先に行ってしまう・・・という不便さもあるのかもしれません。
そういう意味でも、やはり先生と一緒のアンサンブルには代えられません。
生徒さんにいろいろな音色やバランスを知ってもらうため、伴奏を弾くときは私もかなり気合を入れています。
「1オクターブ上で」の弊害
と、アンサンブルの楽しみがある一方で、弊害もあります。
ピアノ・アドベンチャーに限らず、「連弾の時は生徒は1オクターブ上で弾きます」という教本は多いですよね。
生徒がミドルCポジションを習っている段階では、確かにそのままだと伴奏が低音域になり、重たくなってしまいます。
ですので1オクターブ上げる意味というのはよくわかるのですが、これを頻繁にやっていると、譜面上の音が「絶対的な」音の位置を表しているという理解があいまいになっていきます。
つまり、ドならどこのドを弾いてもいいんだ、という誤解を招くということです。
さらに、生徒さんがご自宅で88鍵よりも幅の狭いキーボードを使用していると、そもそもミドルCの位置が教室のピアノと違うという問題も発生するようで、そこにこの「連弾の時は1オクターブ上」の習慣がつくとさらに混乱が増すようです。
ピアノ・アドベンチャーのアンサンブルが美しいのは書いた通りで、どちらを優先するかは難しいところですが、個人的にはせめて導入書の間は、連弾の時もオリジナルのポジションで演奏するようにしてほしいと思います。
この点トンプソンは生徒がオクターブ移動しなくてもいいように伴奏を作っているので、やはり理解の定着を優先したのだなと感じます。
本来はオクターブ移動する、というのは調が変わるくらい大事件ですよね。
エリーゼのためにを1オクターブ上で弾いたら、報われぬ恋の悲しみが薄れてしまうような気がしますし、
子犬のワルツを1オクターブ下で弾いたら猛犬のワルツになります。
だから、初歩の段階で大げさかもしれませんが、どの曲でもオクターブ上げて弾くことができる、という誤解につながらないよう、注意が必要だと思います。
ピアノ・アドベンチャー テクニック・パフォーマンス
さて、ここまでピアノアドベンチャーの導入書について話をしてきました。
今さらですが、ピアノ・アドベンチャーはオールインツーの教材です。
どういうことかというと、レベルごとに「レッスン&セオリー」と「テクニック&パフォーマンス」の2冊に分かれているんですね。
もちろん、本来は生徒さんが2冊一緒に使うことを想定されているわけですが、私は生徒さんには「レッスン&セオリー」のみ購入してもらっています。
以前も触れましたが、ピアノ・アドベンチャーは内容が丁寧な分、そのまま教本に沿って進めていると進度は遅くなりがちです。
どんな生徒さんでも無理なく学べるのは紛れもないメリットですが、時間は短くても自宅で練習してきてくれる生徒さんだと、だんだん教本の方が生徒さんに追い付かなくなってくるという現象が起こります。
さらに考えておきたいのは、ピアノ・アドベンチャーではちゃんとした両手奏が出てくるのが Level 2 以降だということです。
ここは色々考え方が分かれるところだと思いますが、私自身はできるだけ早いうちに両手奏を取り入れたいと思っています。というのも、
・片手ずつ弾くのと両手で弾くのとでは頭の使い方が違う
・片手ずつでメロディーを分担して弾く曲だと、かえってリズムが取りづらい
ということを日々感じているためです。
それを考えると、「テクニック&パフォーマンス」までやるのはやはり過剰な気がします。
とはいえ、先生は「テクニック&パフォーマンス」を1冊持っておくことをおすすめします。
導入書で出てくる曲のねらいがよりわかりやすくなるためです。
生徒さんに何か苦手な単元があれば、「テクニック&パフォーマンス」の曲(初見で弾けます)で補習することもできます。
導入書におススメの併用曲集
先ほども書いたように、導入書レベルでは両手奏はほぼ出てきません。
もし導入書の他に曲集をやるのであれば、両手奏の出てくる曲集を補完的に使うのがよいと思います。
プレリーディングの段階では、おなじみのこちら↓
両手奏と言ってもユニゾンですが、左右の手を同時に動かすという体験には良いと思います。
それから、この「きらきらピアノ こどものピアノ名曲集」は、導入書の Unit 5 あたりから併用できます。
ポップスなど他のジャンルまで手を広げすぎず、「クラシック音楽」の基礎を学ぶにはとてもよいと思います。
導入書の後は?
導入書が終わったら、そのまま Level 1 に進んでももちろん良いのですが、導入書を終える頃には生徒さんの希望もだんだんはっきりしてくると思います。
幅広く、教養としてピアノを習うのであれば、そのままピアノ・アドベンチャーを進めていくのが良いと思います。
もし生徒さんが「もっとピアノを極めたい」と思っているようでしたら、私なら迷わずトンプソンに乗り換えます。
クラシックのピアノを教える身として、生徒さんにはできるだけ早くクラシックのスタンダードなレパートリーに触れてほしいと思います。そこまで最短距離を突っ走るのがこのトンプソンです。
見た目があまり子どもにとって魅力的でない、すべての音に指番号が振ってある、と言ったマイナスポイントも聞かれる教本です。このマイナス・ポイントをどう回避するか?についてはまた別の機会に述べたいと思います。
おわりに
ここまで長々とピアノ・アドベンチャーの導入書について語ってきましたが、いかがだったでしょうか?
あますところなくピアノ・アドベンチャーの魅力を語ってきた・・・はずが、最終結論としてトンプソンに着地するという、やや強引な展開となってしまいました。
それもこれも、この記事を書いている間にも、ピアノ教本についての考えが色々と変わってきたからということもあります。
教本選びって本当に難しいし、特に日本では選択肢が多すぎて悩んでしまうこともあると思います。
でも自分が本当に教えたいことは何か?を考えた時、導入にどの教本を使うかはそこまで重要でないという結論に達しました。
これについてはまた後日書きたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。